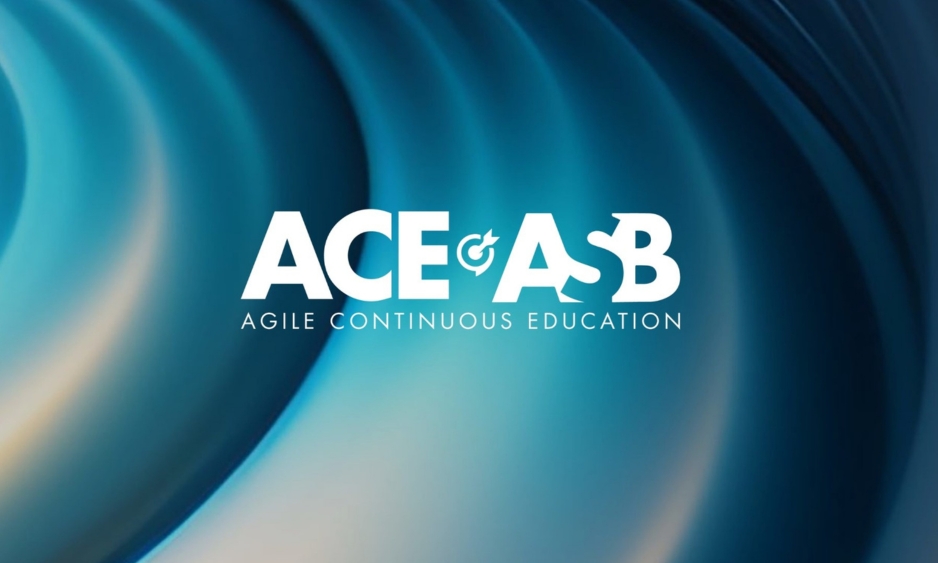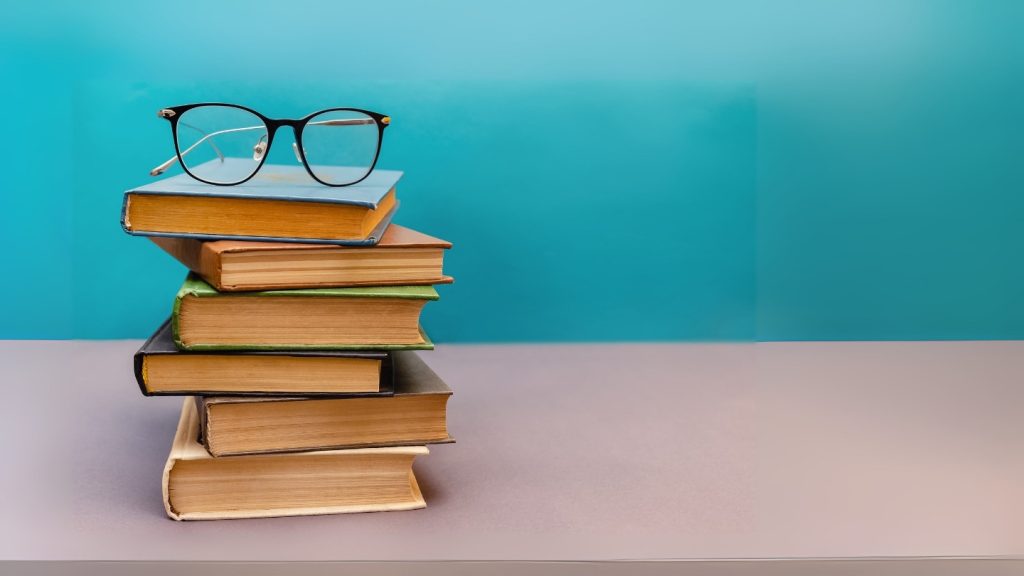この記事の3つのポイント
- アジアの高等教育機関は柔軟性を中心原則とすべきだ
- 高齢化と不確実性の元で生まれる学習ニーズに応えよ
- アジャイルな生涯教育の実現で日本とアジアは共に変革を
マレーシアから日本にいたるアジアの高等教育制度は、なぜ欧米の高等教育制度と違っているのだろうか。アジアの高等教育制度は、欧米と同様、柔軟性を中心原則にすべきだ。これは経済・金融用語で言う、「オプション」を所持することに似ている。
つまり不確実性が解消された時点で、オプションの所有者に意思決定の権利を与えるものだ。この考え方は、不確実性の下における戦略的な意思決定と強く共鳴する。そして日本の科学、工学技術、および政策コミュニティーでは既に高く尊重され、理解されている領域でもある。
教育の柔軟性は、厳格な締め切り、画一的な評価、および固定された時間的または地理的構造の制約を取り除くことで、学習行程を拡充し、その長期的価値を増大させる。この制約がないことで、学問的かつ専門的な道筋や進歩が、個々人のペースや目的によって導かれ、どの進路もそれぞれ独自の到達点へとつながっていくのである。
経済学で言えば、この概念は「パレート効率フロンティア(Pareto efficiency frontier)」に近い考え方だ。リソースと機会が割り当てられ、全体として最も効率的なポイントでトレードオフすることになる。
柔軟性は、職歴、投資、および政策形成を含む、生活の多くの領域で、固有の価値をもっている。その一つの重要な理由は、不確実性がわれわれの未来を形作るということである。不確実性が、世界経済の予測、円の交換率、もしくは予期せぬ人生の出来事の見込みのいずれに関わることであっても、結果を予測するわれわれの能力は、本質的に限られている。
予測不可能ということは、日本では特に実際的な意味をもっている。人口統計学的な変化、労働力不足、急速な技術の発展は、伝統的なキャリアパスの見直しを迫り、そしてその延長として、教育モデルの再評価を促している。
日本人は生涯学習が経済的に必要
人口のほぼ29パーセントが65歳以上で、就労年齢人口も減少する中、日本では、生涯学習はもはや任意の選択ではなく、経済的に必要なものになっている。ロボット工学、高齢者介護、グリーン・テクノロジー(環境保全技術)、およびサイバーセキュリティーのような高度成長部門は、すべて大規模な技能の再習得を必要としているが、日本の今の高等教育は、その厳格なスケジュールと学際的な選択肢が制限されていることで、ニーズをうまくサポートできていない。
同時に、雇用状況も変化しつつある。企業はハイブリッド勤務計画、デジタル雇用の基盤、社内人材の流動性をより強調している。従業員、特に若い世代は、より多くの柔軟性、継続的な成長、およびより良い仕事と生活の統合を提供する職歴を求めている。
日本における伝統的な雇用は、長い間一つの組織で生涯役割を果たすことを意味したが、この変化は顕著だ。教育機関は、こうした専門が深まりかつ個人的なニーズを反映する学習経路を提供することによって、対応しなければならない。
日本は、要素で切り分ける学習カリキュラムと成人教育を通して、柔軟性のある学習を促進し始めているが、非伝統的な学生の参加は低いままである。学部生のうち25歳以上の占める比率は米国の16%に対し、日本では2%未満にとどまっている。
高等教育制度の入学者のうち女性は49%を構成するが、経済協力開発機構(OECD)平均の56%を下回っており、さらにSTEM(科学・技術・工学・数学)分野に進むのは女性のうち7%にすぎない。
Read the full article HERE.
Originally published by Nikkei Asia.